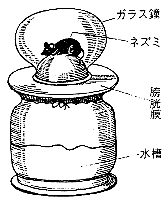| 科学の歩みところどころ |
|
| 第8回 呼吸とは何か |
|
| 鈴木善次 |
|
|
|
生命精気の取り込み
|
|
| 鼻をつまめば息苦しくなる。そうした経験から人々は直感的に生きるのに必要な何らかのものが鼻を通して体の中に取り込まれるものだと考えるであろう。おそらく古代の人々もそうであったと思う。 ギリシア時代になると,いくつかの理論が登場する。心臓で暖められた血液を冷却するために空気を肺へ取り込んでいるのだという説も出れば,生物が生きる活力を与えられる生命精気なるものを取り込んでいるのだという考えも現れた。 こうした説は,いくらかの修正を受けながらも,長い間人々の思考の中に生き続けてきた。上記の生命精気を取り込むという説は,生命精気という言葉を酸素に置き換えれば,今日の考えと大筋においては違わなくなる。ただ酸素は取り出して,その諸特性を示しうるし,実在を証明することができるのに対して,生命精気は人前に示しえない。生命精気の考えを支持発展させたガレノス(Galenos, 約129-約200)は,それを物質的実体であると考えていたようであるが,それを実証する手段を持ち合わせていなかった。もちろん,手段があっても実証しようとしたかどうかは別である。 生命精気が具体的に物質との対応において考えられるようになったのはルネッサンス期以降であろう。12世紀になるとアラビアからヨーロッパへ錬金術が入り込み,新プラトン主義と結びついてパラケルスス(Paracelsus, P.A., 1493-1541)に代表される生命観が登場する。ちなみに彼は新プラトン主義でよく用いられた大宇宙,小宇宙の考えに基づき,人体を小宇宙になぞらえ,体内の臓器と惑星とを対応させ,病状の判断や治療方法を考えている。ところで,アラビアから伝えられた錬金術では万物の根源となる元素としてギリシアからの四元素(火・空気・水・土)説では不十分だとして可燃性のもとになる硫黄,流動性のもとになる水銀という原理を考えた。パラケルススはそれに可溶性のもとになる塩を加え,いわゆる錬金術における三原理説を作り上げた。パラケルススは,そのうちの硫黄が生命力を持った空気の成分であると考えた。この生命力を持った空気が物を燃やし,生命を維持するのであろうという。ただし,硫黄のほかに補助的に硝石が必要であるとも考えている。 |
|
|
硝石様物質の取り込み
|
|
| 17世紀になると,パラケルススが補助的に必要だと考えた硝石が重視されてくる。パラケルススの後継者の一人イギリス人のフラッド(Fludd, Robert, 1574-1657)は1619年に出版した『超自然宇宙誌』で生命力を持った空気の成分が硝石性であるという考えを述べているという。また,前回登場したヘルモント(Helmont)も生命精気と硝石が似たようなものであると考えている。硝石を燃やし,そこから出てくる気体の中では,確かに物がよく燃えるし,動物も長く生きる。こうした経験が上記のような考えを生み出させたのであろう。 イギリス人のメイヨー(Mayow, John, 1640-1679)もまた硝石を重視した一人である。彼はボイル (Boyle, Robert, 1627-91) やフック (Hooke, Robert, 1635-1703) などの研究によって明示された空気の弾力性の原因を,この硝石から出る気体,いわゆる硝石様物質と関連づけている。彼によれば,空気には隙間があり,その隙間に硝石様物質の粒子が入り込んでいる。この粒子に弾力性があるために,空気全体にも弾力性が出るのだという。
|
|
|
脱フロギストン空気から酸素へ
|
|
| メイヨーの研究はある意味で現在の酸素の発見であり,それに基づく呼吸作用の解釈に近づいていたものであった。しかし,その後,人々に十分認められることなく,17世紀末から18世紀初頭におけるイギリス科学界の衰退とともに忘れられた。 17世紀末からドイツでは医化学派と呼ばれる一派が台頭してきた。いわゆる錬金術派の硫黄・水銀・塩の三原理を重視する立場にたつものである。その中の一人ベッヒャー(Becher, Johann Yoachim, 1635-82)は硫黄の原理に相当するものに「油性の土」という名をつけ,これがあらゆる可燃性物質の中に含まれていて,燃焼はこれが他の物質と分離する現象であるとした。彼の後継者のシュタール(Stahl, Georg Ernst, 1660-1734)はこれを受けて,1703年に「油性の土」にフロギストン(phlogiston)という名称を与えた。いわゆるフロギストン説の登場である。『化学の基礎』(1697)は彼の代表作であり,この中でフロギストンの理論が展開されているという。 18世紀も半ばになると前回の「気体の発見」でも知られる如く,気体に関する研究が活発になってくる。これにはその当時からの産業革命など社会的背景が関連していることは想像に難くない。その気体の研究にフロギストン説が大きくかかわり,この説に基づく現象の解釈が流行した。 前回(第7回)登場したイギリスのプリーストリ(Priestley,Joseph,1733-1804)もその一人である。彼は動物の呼吸には空気をフロギストン化する性質があると論じている。フロギストン化するということは,空気がフロギストンで飽和されるという意味である。従来から物の燃焼と動物の呼吸の類似性が気づかれていたが,フロギストン説でも同様に扱われ,フロギストン化された空気の中では動物は長く生きられないと考えられた。 このプリーストリが1774年10月にパリを訪れ,,ラボアジェ(Lavoisier, Antoine Laurent, 1743-94)に「フロギストンを失った空気」,いわゆる脱フロギストン空気の発見の話をした。これがきっかけとなってラボアジェによる酸素の発見がもたらされることになる。これらについては前回の記事をお読みいただくことにして,ここでは呼吸に関連する話に限定しよう。 1777年5月3日ラボアジェは科学アカデミーで,“極めて呼吸に適する空気”という論文を発表している。その中でプリーストリのフロギストン説に基づく呼吸の解釈の矛盾点を指摘しながら,水銀の酸化実験と動物の呼吸実験を比較し,プリーストリの言う“脱フロギストン空気”がまさに“動物の呼吸に適する空気”であり,物の燃焼や動物の呼吸の際には,これが空気中から使われるのだということを定量的に示した。彼はこの論文ではまだ「酸素」という言葉を使っていないが,同年9月5日づけの論文では“脱フロギストン空気”に変えて「酸素」という名を提唱している。彼はこの気体が酸を作り出す成分と考えてそのような名を与えたわけだが,酸の元は本来「水素」であることはご承知の通りである。 |
|
|
呼吸における二酸化炭素
|
|
| ところで,ラボアジェの研究で大切なことは上記の論文中で明らかにしていることであるが,動物の呼吸に際して二酸化炭素が排出されることを実験的に示していることである。 彼はフランス・スズメをガラス鐘内に閉じ込め,約1時間,スズメの呼吸の様子を観察している。スズメは55分で死亡し,ガラス鐘内の空気ははじめの約60分の1減少していた。これは水銀をフラスコ内で燃焼させたときの5分の1の減少に比べるとはなはだ少ない数値である。あとに残った空気の中ではローソクは燃えないし,新たに動物を入れてもすぐに死ぬ点では,水銀の実験の場合と同じである。ただ,石灰水を白濁させる点では,水銀の場合とは異なっていた。 ラボアジェはこのあとに残った空気を苛性アルカリと反応させてみた。すると体積が6分の1近く減少し,さらにアルカリがその腐食性を失い,酸で発泡するという性質に変化した。これは1761年にブラック(Black, Joseph, 1728-1799)が発見した固定空気(fixed air)の持つ性質と同じものであった。ラボアジェは固定空気という言葉の代わりに,“白亜から得られる酸”という意味から「白亜酸」という名を与えた。今日の二酸化炭素(炭酸ガス)も時代により,人によりさまざまに呼ばれてきたのである。 その後,1780年にラボアジェはラプラス(Laplace, Pierre-Simon, Marquis de, 1749-1827)と共同でより精密に呼吸に際しての酸素の取り込み,水及び二酸化炭素の生成を定量的に測り,また熱の発生量も測定し,動物の熱は体内の養分が燃焼するときの化学反応熱に由来するものであり,呼吸と燃焼は本質的には同じ現象であると考え,“呼吸とは体内における緩やかな燃焼である”と論じた。もちろん,これは現在からみれば,あまりにも短絡的な類比であるが,呼吸現象の解明を一歩前進させた彼の功績は大きなものであった。 |
|
|
呼吸の本質
|
|
| 呼吸が体内でのエネルギー獲得のための働きであるという本質的な理解は20世紀を待たなければならなかったが,19世紀はラボアジェの研究と現在の研究とを結びつける重要な時期であった。この時期に動物ばかりでなく,植物でも上記のような酸素の吸収と二酸化炭素の排出が行なわれていることの実証がなされたことである。18世紀にもヘールズ(Hales, Stephen,1677-1761) ,プリーストリ,インヘンフース(Ingenhousz, Jan, 1730-1799),スヌビエ(Senebier, Jean, 1742-1809)などによる先駆的研究があったし,19世紀に入るとその延長としてソシュウル(Saussure, Nicolas Theodore de, 1767-1845)による定量的研究(1804)が見られるようになる。しかし,植物の場合には光合成があるため,呼吸だけのガス交換の定量化がむずかしく,なかなか植物の呼吸と動物の呼吸の同一性が認識されにくかった。それを可能にさせたのが1850年のガリュウ(Garreau, Lazare, 1812-?) の研究であったという。今,その詳細を知らないが,光合成が行なわれている最中での呼吸に伴うガス交換の測定方法を編み出したようである。 また,微生物の行なう発酵現象の解明が呼吸の本質の理解に関わっている。19世紀はその発酵現象を含めて微生物に関する研究が進展した時期である。さらにエネルギー概念の成立も不可欠である。これに関しては他の機会で取り上げられているのでここでは省略するが,いずれにせよ,いろいろな分野の研究が進み,それらが総合化されることによって一つの現象の本質が見えてくることが科学史の上ではしばしばあるものである。 こうして今日では細胞というレベルでの呼吸作用の全貌がほぼ明らかにされるようになった。呼吸とは生命精気を取り込む働きであるという考えから呼吸とはミトコンドリアでの ATP 生成作用であるという理解への道のりは,他の知識獲得の場合と同様,長く,そして曲がりくねったものであった。 |