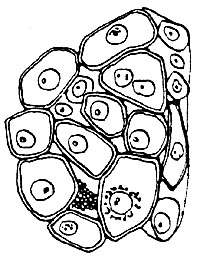| 科学の歩みところどころ |
|
| 第6回 細胞説の成立 |
|
| 鈴木善次 |
|
|
|
卵も細胞
|
|
| しばしば生物細胞の中で一番大きなものは何であろうかという問答がなされることがある.そのときに用意される答がダチョウの卵である.卵といっても日常語のたまごではなく,その中に入っている卵細胞である.卵黄を大量に含んだ卵が1つの細胞であることを納得するのに時間のかかる人も多くみうけられる.細胞といえば,すぐタマネギの表皮で見たものを思い出すからであろうか. 私たちのこうしたとまどいは比較的短時間の学習で解消される.解消されるといってもある意味では押しつけによってそうした常識を植えつけられるのかも知れない.全ての生物のからだは細胞からできているのだという常識から卵も細胞であるという常識を演繹的に導きだす人がおおかたではなかろうか. しかし,そのあたりに科学教育上の観点から再考せねばならぬ問題がかくされているような気がする. |
|
|
顕微鏡下に見るもの
|
|
| 中学を卒業するまでに「理科」の授業で,植物の葉などを使って生きもののからだのつくりを顕微鏡下で見る機会があるであろう.とくにタマネギの表皮ではいくつにも区分けされた模様を明確に知ることができる.同様な経験をいくつかの植物体でえた子どもたちがいたとしよう.はたして,この子どもたちはすなおに卵も細胞であることを納得するであろうか. この子どもたちと同様な状況が17世紀の顕微鏡学派とよばれる人たちにもあてはまるのではなかろうか.17世紀といえばガリレイやデカルトたちの登場した時代,近代科学の誕生期である.自然現象を理性を通して解明しようという風潮の見られたときであり,前世紀に現れた顕微鏡もそのための武器として即座に利用されることになった.物理学者ボイルの助手であったR.フック(Robert Hooke,1635〜1703),あるいはイギリスの医者N.グルー(Nehemiah Grew,1641〜1712),イタリアの解剖学者M.マルピーギ(Marcello Malpighi,1628〜94)たちはそれぞれに目的をもって顕微鏡下に生物の姿や,そのつくりを追った.
フックにくらべると,グルーやマルピーギはより生物学的であった.これは彼らがいずれも医学畑の人であり,解剖学の伝統の中に位置していたからであろう.その彼らが顕微鏡を武器にして顕微解剖学という新分野を開いた.1672年の『植物の解剖』(グルー),『植物解剖学』(マルピーギ)の2つの著作はその記念樹でもある. グルーの著作は1682年のものが現在復刻され入手しやすくなっているが,そこに描かれた解剖図はまことにすばらしいスケッチである.ただ気にかかるところは,細胞の壁があたかも織物のたて糸,よこ糸であるかのように描かれているものがあるからである,実際,彼はそのように細胞を理解していたようだ. マルピーギは植物を対象としただけでなくご存知の昆虫のマルピーギ管という名称からもわかるように動物にも広げており,植物と動物の類似性にまで話しを展開しようと努力したが,技術的な限界もあって細胞説を生みだすまでには至らなかった.動物の組織というものは見にくいものである. |
|
|
情報の集積
|
|
| 17世紀の顕微鏡学派による先駆的研究は結局,生物体の本性をえぐるところまでには至らず,しばらく生物学者たちの関心事が他へむけられたこともあって中断した形であった.18世紀はリンネの分類でも代表されるように,生物界の秩序をさぐるなどマクロ的な研究が盛んであった. 19世紀に入ると事態は一変した.生物学者たちは再びミクロのレベルへ関心を示しはじめた.その要因として考えられることはアミチらの努力による顕微鏡の改良等研究技術の進歩もあげることができるが,物理学,化学の分野での進展,とくに分子・原子概念による自然現象の解釈が進んだことが影響を与えているように思われる.物質にみられる基本単位という考えを生物体にもあてはめ,生命現象を物理科学の方法で解明しようとする,いわゆる還元論の傾向が現れてきたのである. 生物体の基本的単位は何であろうか.顕微鏡学派によってスケッチされた細胞がそれにあたらないのであろうか.そのことを確かめるためには,まず細胞が1つ1つ独立した存在であるかどうかということを知ることである.その役割をはたしたのがドイツのトレビラヌス(G.R.Treviranus,1776〜1837)やフランスのデュトロシェ(H.J.Dutrochet,1776〜1847)たちである.トレビラヌスは1805年に植物体の切片をあらっぽく扱うと細胞がばらばらになることを示しており,デュトロシェは1824年に硝酸で煮るとばらばらになることを報告している.これらは今日の塩酸を用いて根端などをばらばらにして観察する技術の先駆をなしているわけである.いずれにせよ,細胞が1つ1つ切りはなされることは,グルーのような考えの否定になるし,研究対象が組織というレベルから細胞というレベルへ移ることにもなる. 細胞レベルの研究となれば,当然その内容物や構造に関心がむけられる.観察技術の進歩と相まって,まず大きな前進となる発見がR.ブラウン(Brown,1773〜1858)によってなされた.彼はスコットランドの植物学者であり,18世紀以来の伝統をうけついで分類学,特にオーストラリアの植物相についてすぐれた研究をしていた.そうした中でラン科の植物細胞中に彼の言葉を借りれば,“1個の円形の領域”,“はっきりした粒状の領域”すなわち核を見出した.すでに1781年にF.ホンタナによって動物細胞中に核がみることが見出されていたが,十分注目されなかった. ブラウンはラン科以外の植物(ただし種子植物)についても核の存在を確かめ一般化している.このあたりの手続きは理科の授業においても大切なことであり,タマネギだけですますべきでないと思う.できれば,動物細胞の中の核の観察も試みさせてほしい. |
|
|
細胞説の提唱
|
|
|
ブラウンによる核の発見を意味あるものに高めたのはドイツのシュライデン(M.J.Schleiden,1804〜81)であろう.しばしば細胞説の提唱者としてこのシュライデンと後述のシュヴァンがとりあげられることに対して,批判する人がいるが,それらは時には愛国主義的発想であったり,シュライデンの名誉欲の強さに対する非難であったりする場合がある.細胞説を“細胞が生命活動の基本単位である”という形で定義をすると,彼らの役割は大きくなるのである.生命活動の基本単位であるからにはそれら細胞がどのようにして出来てくるのかまで論及しなければならない.彼らはそれをやっているのである. シュライデンはブラウンの発見した核と細胞形成とを関連づけた.当時の結晶学の知識を活用し,結晶の成長がなされるのと同様な様式で細胞は核を源にして新生されると解釈をしている.これは今日からみれば大きな誤りを犯したことになるのだが,細胞形成という問題に人びとの関心をむけさせたことは意義があったといえよう.
細胞形成に関する真の姿は19世紀の末まで明らかにされなかったが,シュヴァンの説は植物と動物の境界を大きくとりはらい,植物学,動物学という分野を生物学という1つの分野にまとめあげる役割をはたしたのであった.私たちはこうした歴史的過程の中に,子どもたちがもっているタマネギの細胞とニワトリなどの卵との間の壁をとりはらう手だてを見出すことができるのであろう. |