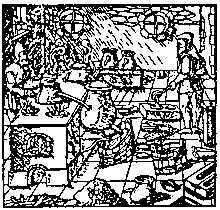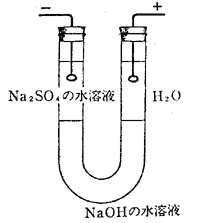| 科学の歩みところどころ |
|
| 第5回 酸とアルカリ |
|
| 森 一夫 児島昌雄 |
|
|
|
酸・アルカリの語源を検索すると
|
|
| 化学の世界で重要な位置を占める酸・アルカリの概念は,紆余曲折を経ながら今日に至っている. 人類は古くから,柑橘類の果汁や酸など,すっぱい味のする物質があることを知っていた.この物質は,その味もさることながら,金属を腐食したり,ミルクを凝固するといった特別の性質があるため特に関心がもたれ,「酸(acid)」とよばれてきた.この言葉は,ラテン語の acere(すっぱい)という語に由来している.中世の錬金術師たちは,黄金や不老不死の妙薬のもとになる“賢者の石”を探していたとき王水や硝酸などの強酸を発見し,酸の仲間を増やしていった. 一方,酸と反応してその働きを弱める物質もまた,昔からわかっていた.それは,脂肪を落とす洗剤として使われていた木灰の中にあった.木灰の汁を煮つめてできた粉末の物質は,舌をさす特有の鹹 (から) 味があり,アラビア人によって「アルカリ(木灰の意味)とよばれていた.この物質を強熱すると,灰の一部は気体(主に二酸化炭素)となって消え,さらに強いアルカリ性物質が残る.当時の人たちは,加熱した後に残る部分はもとの灰よりも堅固な物質だと思い,ギリシア語の basis(基礎)」にちなんで base(塩基)と名づけた.今日,酸の対概念には塩基を用いるが,水に溶けやすい無機塩基はアルカリともいっている.
この頃はスミレなどの草花の汁が酸・アルカリの同定に使われている.ちなみに,今の小学生たちは,地中海沿岸でとれるリトマスゴケの青色色素から作られたリトマス紙を用いているが,第二次大戦中は,このリトマスゴケがわが国に輸入できなくなり,ヨコサルオガゼで代用したというエピソードがある. |
|
|
酸の粒子はとがっている?
|
|
| 実用的色彩の強かった化学も,17世紀に入ると自然科学の一分野としてしかるべき地位が与えられるようになり,酸・アルカリも,なぜそうした性質を示すのかという点にまで目が向けられていった.ボイル(1627〜91)やレメリらは,当時流行の粒子観に基づき,粒子の大きさや形状で酸・アルカリの性質や現象を説明づけようとする.例えば,酸は先のとがった針のような粒子からできているため,舌を刺激してすっぱく感じるのだとか,金属の粒子の間に入り込むから金属は溶けるのだと主張した.一方,アルカリはといえば,これは多孔質の固体であり,酸の粒子がこの穴に入るから酸の性質が失われるというのである. こうした機械論的な説明はまだ概念的なにおいが強く,代わって,化学的特性を備えた元素という概念で酸・アルカリを説明しようとする一派が次に現れてくる.彼らこそ,今日の化学者の直接の先祖といえる. |
|
|
酸素を含む酸,含まない酸
|
|
| 産業革命によって大量に生産された布を漂白するのに,石灰水が使われるようになってきた.石灰の研究から,固定空気(二酸化炭素)が発見され,それが端緒となって,水素,そして酸素が見つけられた.この酸素が炭と結びつくと炭酸ができ,硫黄と結びつくと亜硫酸,そして燐とならば燐酸ができる.どうも金属以外の物質がこの気体と化合すると酸になるようだ.そこでラボアジェ(1743〜94)は,すべての酸は酸素からできていると考えた.「酸素(oxygen)」は,酸をつくるもとという意味で,彼が命名したものである.なお,「酸素」という和訳は,江戸時代の学者,宇田川榕庵の著書『舎密開宗』に初めて登場した. ラボアジェの説では,塩酸も酸である以上は酸素を含まなければならない.彼は塩酸が未知の元素の酸化物であり,この酸化物(塩酸)がさらに酸化されて生じる気体を「酸化塩酸」と名づけた.ところがデービー(1778〜1829)は,この気体を加熱した木炭上に通したり,酸素を含まない化合物と反応させたりして酸素を取り出そうとしたが,どうしても酸素は得られなかった.デービーは,「酸化塩酸」は単体だと考えて,塩素という名前に変えた.彼はまた,塩素と水素を混合して火花をとばすと塩酸が合成できることから,塩酸は酸素ではなくて水素を含むと考えるようになった.こうして,酸素を含まない酸もあることがわかり,ゲー・リュサックによって,酸には「酸素酸」と「水素酸」があるという見解が発表された. その後,酸化カルシウムのような酸化物が酸と反応して無水の塩と水が生成することに注目したデュロンは,酸の中の水素と酸化物の酸素とが結合して水が生じたと推測した.さらにリービッヒ(1803〜73)は,有機酸の塩基度の研究から,一塩基酸は金属と置換される水素を一原子,二塩基酸ではそうした水素を二原子もっていることに気づいた.このような事実から彼は,酸とは水素の化合物であり,その水素原子は金属によって置換されるという仮説を提出したのである. |
|
|
イオン説の登場
|
|
こうした説に対しアレニウス(1859〜1927)は,電圧を加えなくても,電解質分子はイオンに解離しており,そのイオンが独立分子のように行動するという仮説を唱えた.例えば,塩酸を電気分解するとイオンになって,陰極に水素,陽極に塩素を発生するが,電圧を加えなくても水中で両イオンに解離しているというのである.そうすると,酸の性質を示すのは水素でなく水素イオン(H+)だ,という考えが生まれても決して不思議ではない.彼は,酸とは水溶液に水素イオン(H+)を放出する化合物であり,塩基は水酸化物イオン(OH-)を放出する化合物だと,新教育課程では高校生も学習する定義を下した. アレニウスの酸・塩基の定義を使うと,酸や塩基の強さを論じることができ,定量化への道が開けたものの,残念ながら水溶液以外の溶液では,酸・塩基を論じることができない.それに,何よりも大きな問題はH+の存在である.H+は水素の原子核(陽子 (プロトン))であって,この正電荷の高密度なイオンが水溶液中に単独に存在するとは考えにくい.やがて,水がH+を受けとってヒドロニウムイオン(H3O+)になっていると解釈されるようになる.この考えを発展させたブレンステッドとローリーは,他の物質にH+を与えることのできる物質を酸,H+を受けとることのできる物質を塩基と定義した.この理論は,水以外の溶液にも使えるだけでなく,従来の酸・塩基の概念をも包括している. いままでの定義をみていると,酸の定義の主役として水素が関与していたことがわかる.では,BF3のようなものは酸とはいえないのだろうか.こうした疑問からルイスは,水素に頼っていた従来の説を一掃して,配位結合する場合の電子対受容体を酸,電子対供与体を塩基と定義するのである. 例;BF3(酸)+:NH3(塩基)→BF3ーNH3 ルイスの説は,ブレンステッドらの定義をも含みこんでしまい,さらに広い範囲で酸・塩基概念を使用できるという点で,より一般化された理論といえよう. ルイスが定義した酸・塩基の反応を調べていると,互いに結合しやすい2つのグループのあることがわかってきた.そこでピアソンは,酸・塩基には硬・軟の2つの種類があるという考えを提案した.硬い酸・塩基とは,原子や原子団が分極しにくい酸・塩基のことであり,H+,Mg2+などが硬い酸,OH-,F-などが硬い塩基の部類に入る.この硬い酸と塩基同士が反応すると,極めて安定なイオン結合性の化合物をつくるのである. このように,酸・塩基の概念は学問の進歩とともに,移り変わってきたのである. |